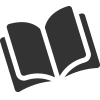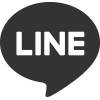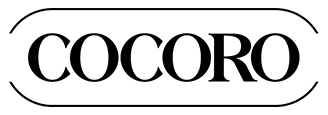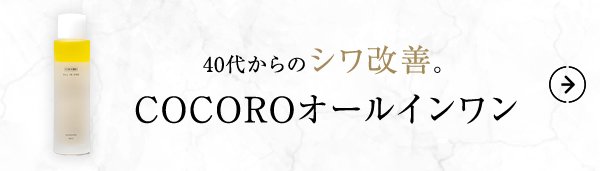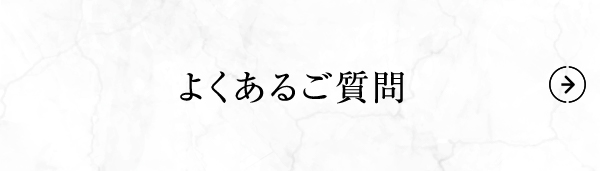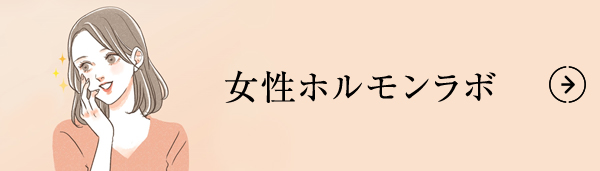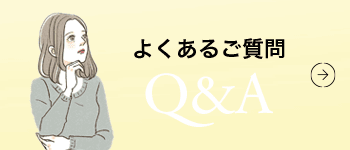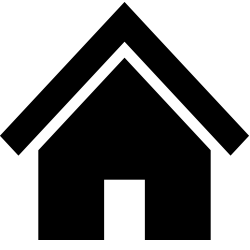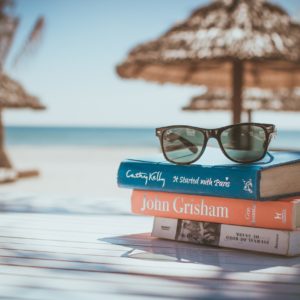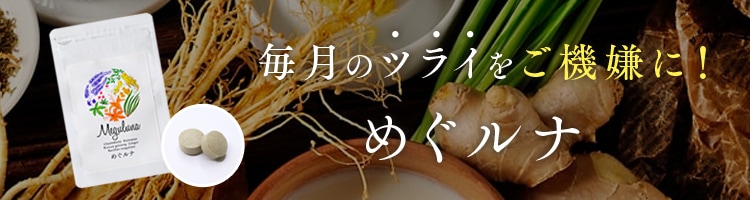夏の水分補給に-紫蘇(シソ)は日本のメディカルハーブ

ハーブのある暮らしで、毎日に彩りを。
ハーバリスト 岩橋たか子先生が綴るコラム「ハーブの庭」。
季節のハーブのおはなしやアレンジレシピなどをご紹介。
今回は、夏にオススメのハーブのおはなしです。
夏本番!意識した水分補給を
夏は湿度、温度ともにさらに上昇する季節。熱中症に関するニュースが後を絶ちません。水分補給は年間通じてとても大事なのですが、特にこの時期は定期的に意識した水分を摂る必要があります。ただ、単純に水を飲めばよいかというと、そうでもなく体内にいかに効率よく水分を吸収させるかも大事になってきます。
そこで今回は、夏におすすめのハーブを使って水分吸収率をあげるだけではなく、体調を整えて夏バテを防ぐ活用のポイントをお伝えします。
紫蘇(シソ)は日本のメディカルハーブ!

今回おすすめするハーブは、「紫蘇(しそ)」です。シソ科の一年草で、日本や中国をはじめとする東アジアで古くから親しまれてきた伝統的で身近なハーブといえます。特に梅雨から夏にかけてスーパーなどの店頭に出回り、梅干しと一緒に漬けたり、シソジュースにしたりと活用されてきました。葉の色によって赤紫蘇と青紫蘇(大葉)に分けられ、用途や風味もそれぞれ異なります。
生薬として、主に赤紫蘇が「蘇葉(そよう)」と呼ばれ、古代から薬用植物として重宝されてきました。その名は、「蘇(よみがえる)」ほどの効能をもつ葉、という意味に由来するとされています。
紫蘇を夏におすすめする3つの理由
その紫蘇ですが、夏におすすめの理由を、以下に3つ纏めてみました。
発汗・解熱作用
体内の熱を冷まし、汗をかきやすくすることで、夏の暑さによる体のだるさをやわらげることにあります。
消化促進・食欲増進
夏バテで落ちがちな食欲を回復し、胃腸の働きを助けます。
抗菌・防腐作用
食中毒が心配な季節にも心強い存在です。
紫蘇は夏に寄り添う万能ハーブ
薬膳(食材)としての紫蘇には気の巡りを良くする作用(ストレスや暑さで滞りがちな「気」の巡りを整える)があるとされます。※ここでいう「気」とは、からだを動かし、心身を巡らせるエネルギーのようなものです。
青紫蘇は、夏場は薬味として大活躍ですが、香り成分「ペリルアルデヒド」による消化促進や防腐作用が期待でき、暑さと湿気で疲れやすいこの季節には最適なハーブです。
紫蘇は薬味としてだけでなく、毎日の食卓で手軽に取り入れられる万能ハーブです。簡単に紫蘇をみじん切りにし、バジルのようにオイルと合わせてペーストにすれば、保存もできるしパスタやご飯のお供にもなります。おにぎりや冷や奴のトッピングに 刻んだ青紫蘇を添えるだけで、香りと食感にアクセントが加わります。
スーパーで購入したが余った、または自分で育てて大量に収穫したシソの消費に困るといったことがあれば、紫蘇は冷凍や塩漬け、乾燥などで保存も可能。余った葉も無駄なく使えます。紫蘇は、香りと薬効を兼ね備えた、日本の夏に寄り添うハーブです。
水分吸収をサポートする-紫蘇ジュースのつくり方と飲み方
今回、ハーブの活用法でご紹介する「紫蘇ジュース」は、水分吸収に必要な糖やビタミン、ミネラル分を含んでいます。ただ、水分の吸収率をあげるためには、「塩分」も大事なのでシソジュースを水や炭酸で割って飲むときに、ひとつまみだけ自然塩をまぜると水分吸収率が格段にあがり、体内に効率よく吸収されます。ぜひ意識してみてくださいね。
紫蘇だけでなくハイビスカスでシロップジュースを飲む時にもこの方法で水分の吸収と代謝が期待できます。
紫蘇ジュースを作ってみましょう
用意するもの

・紫蘇 300g
※スーパーで袋売りされているものの大体1袋の葉の重さ
・水 2L
・砂糖 300~600g
※白砂糖、グラニュー糖、きび糖などお好みで/量もお好みで調整
・リンゴ酢 150g
・保存瓶 ※事前に熱湯消毒をしておく
作り方

①紫蘇を茎から一枚ずつ丁寧に外して軽く水洗いして水をきっておく。
②鍋に熱湯を沸かして紫蘇の葉を入れて、15分くらい煮込む。
※シナモンやカルダモンなどスパイスと一緒に煮てもOK風味と香りがさらによくなります。
③粗熱が取れたらザルで液をこし、さらにザルの上からゴムベラなどで押しつけるように絞る
④こした液を鍋に戻し、砂糖を加えて弱火にかける。砂糖が完全に溶けたら火を止め、粗熱を取る。クエン酸を加え(りんご酢で作る場合もここで加える)、よく混ぜてから、完全に冷ます。

作ったシロップは水や炭酸で割って飲んでも、ホットで飲んでも美味しくいただけます。その際にひとつまみの塩を入れると熱中症対策の水分補給には最強のサポーターとなること間違いなし!です。
体調を崩しやすい時期だからこそ、旬の恵みを取り入れて、健やかに過ごしましょう。
素敵なハーバルライフを